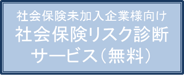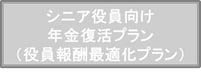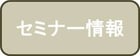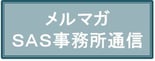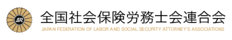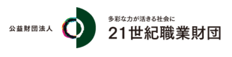最高裁で判断された妊娠や出産を理由とした不利益取扱いの禁止
文書作成日:2014/11/25
先月、妊娠を理由にした降格が「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(以下「均等法」という)に違反するかどうかが争われた訴訟の判決が、最高裁で言い渡されました。育児休業を取得し、職場復帰する女性従業員が増加する中、今後の企業の労務管理に大きな影響を与える内容であるため、今回はこの内容についてとり上げます。
1.今回の最高裁判決のポイント
今回の訴訟は、広島市内の病院に勤務し、勤続約10年で副主任となった女性が勤務先の病院を訴えたという事件です。その女性は副主任に就いた後に、妊娠が分かり、労働基準法65条3項に基づく軽易な業務への転換を請求したところ、負担の少ない部署に異動となり、その際、副主任の地位を外されましたが、復職後についても副主任に任命されませんでした。そのため、この取扱いが、均等法9条3項に違反する無効なものであると主張して、損害賠償を求めていました。
これに対し、最高裁は、妊娠や出産を理由にした降格は、本人自身の自由な意思に基づく合意か、業務上の必要性について特段の事情がある場合以外は違法で無効とする判断の枠組みを初めて示しました。そのうえで、今回のケースは降格について、女性は渋々受け入れただけで明確な同意はなく、病院が取った措置について特段の事情があったかどうかの審理が尽くされていないとして、女性側敗訴とした二審判決を破棄し、審理を広島高裁に差し戻しています。最高裁が示した判決の骨子をまとめると、以下のようになります。
原則:妊娠や出産を理由にした降格は禁止
例外:①自由意思に基づく承認が認められる
⇒今回は、明確な承諾は認められない
②業務上の必要性に特段の事情がある
⇒今回は、不明のため審理を差し戻す
2.妊娠・出産等を理由とする不利益な取扱いの禁止とは
次に、今回の訴訟で争いとなった均等法および労働基準法が定める妊娠・出産、産前産後休業の請求等を理由とした不利益な取扱いの中身を確認しておきましょう。厚生労働省が定める指針では、以下の11の項目を不利益な取扱いとして禁止しています。
①解雇すること
②期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
③あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、その回数を引き下げること
④退職または正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
⑤降格させること
⑥就業環境を害すること
⑦不利益な自宅待機を命ずること
⑧減給をし、または賞与等において不利益な算定を行うこと
⑨昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
⑩不利益な配置の変更を行うこと
⑪派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと
今回の判決を受けて、企業としては上記の取扱いをしていないか確認し、妊娠・出産等にまつわるトラブルを未然に防止していきたものです。具体的な取扱いについてご相談がありましたら、当事務所までお気軽にご連絡ください。
■参考リンク
厚生労働省「男女雇用機会均等法のあらまし」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/danjyokoyou.html
※文書作成日時点での法令・情報等に基づく内容となっております。